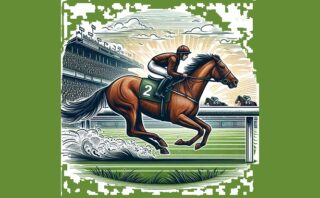.
災害は予測不能、日頃からの備えが命を守る
地震や台風、火災など、いつどこで災害が発生するかは誰にもわかりません。
そのため、普段からしっかりと備えておくことが非常に重要です。
特に、大切な家族や身近な人を守るため、防災士が厳選した「防災グッズ39点セット」をおすすめします。
防災グッズはココで購入すればセットになっているので必要な物は全て揃っています。
防災士推奨!防災グッズ39点セットとは?
このセットは、防災のプロフェッショナルである防災士が厳選した、
災害発生後の3日間を生き抜くためのアイテムが揃っています。
非常食や飲料水、救急用品、防寒・防水用品、照明・通信機器など、必要不可欠なアイテムがしっかりと39点詰め込まれています。
防災士とは?
防災士は、災害時に自助・共助・協働の原則に基づいて行動できるスキルを持ち、防災力の向上に貢献することが求められる資格です。日本防災士機構が認定しており、地域社会や個人の防災意識を高める役割を果たしています。
39点セットの中身
- 非常食・飲料水:災害時に必要な栄養と水分を補うためのアイテム。
- 救急用品:怪我や病気に備えた救急セット。
- 防寒・防水用品:寒さや雨風から身を守るための防護アイテム。
- 照明・通信機器:停電や緊急時に役立つライトや通信機器。
この防災グッズの特徴
- 高品質・長期保存可能:素材にこだわり、長期間保存できるよう設計されています。
- おしゃれなデザイン:カジュアルで日常生活にも馴染むデザイン。リビングや玄関に置いても違和感がなく、いざという時にすぐに使えます。
- コンパクトで持ち運びやすい:軽量でコンパクトな設計のため、簡単に持ち運びが可能。
- 10年間の交換保証付き:長期間安心して使えるよう、10年間の交換保証が付いています。
実際の使用例とユーザーの声
ユーザーAさん(30代女性・会社員)
「地震が夜に起きた際、この防災グッズが大活躍しました。停電中でもセットに入っているLEDライトのおかげで、
家族全員が安全に避難場所まで移動できました。また、リュックが軽量なので、
荷物が多くなりがちな子供連れの避難でも移動しやすかったです。非常食もおいしく、安心して3日間過ごすことができました。」
ユーザーBさん(50代男性・自営業)
「自宅は山沿いにあり、毎年台風シーズンが怖かったため、購入しました。
昨年、台風による停電が数日続いたとき、防災グッズの携帯用バッテリーで携帯電話を充電でき、
安否確認や情報収集ができました。特に、災害時は通信が命綱になるので、
こうしたグッズがすぐに使える状態にあるのは大きな安心です。」
ユーザーCさん(30代女性・主婦)
「新築祝いに友人からプレゼントされました。防災グッズというと無機質なイメージがありましたが、
デザインがシンプルでおしゃれなので、リビングに置いていてもインテリアに馴染んでいます。
子供たちと一緒に避難訓練を行い、実際に防災リュックの中身を確認しながら使い方を学べたので、
万が一の時も慌てずに行動できそうです。」
ユーザーDさん(60代女性・年金受給者)
「高齢のため、避難する際の移動に不安がありました。防災グッズセットに入っていた軽量な携帯用の椅子がとても役立ちました。
避難所までの長い道のりで、何度か休憩をとることができ、疲労を軽減できました。
また、セットには必要な薬や衛生用品も揃っていて、緊急時にも落ち着いて対応できました。」
ユーザーEさん(40代男性・会社員)
「職場でも防災意識が高まり、社員全員にこの防災グッズを備えることにしました。
実際に訓練を行った際、防水ポンチョや非常食など、すべてが必要な状況を想定した作りになっていると感じました。
防災士が厳選したということで信頼性が高く、社員一人ひとりの安全確保にも役立っています。」
ユーザーFさん(20代男性・大学生)
「一人暮らしの身として、防災意識は高く持っていましたが、どんなグッズを揃えればよいのか分からず悩んでいました。
このセットは、必要なものがすべて揃っていて、安心感があります。
特に、手動で充電できるラジオ兼ライトが便利です。非常時でも情報を得ることができるので、今後も重宝しそうです。」
ユーザーGさん(40代女性・主婦)
「家族のために購入しましたが、先日子どもの遠足でハイキングに出かけた際にも、
この防災グッズの中の救急セットを持参しました。子どもが軽い怪我をしたときにも、
すぐに応急処置ができ、とても役立ちました。防災目的だけでなく、
普段の生活でも使えるアイテムが含まれているのは魅力的です。」
ユーザーHさん(70代男性・年金受給者)
「近年の地震や豪雨を受けて、初めて本格的な防災セットを購入しました。軽量で背負いやすく、
体力がない私でも無理なく持ち運べる点が気に入りました。
また、普段使っている補聴器の電池をストックしておくためのスペースも十分に確保できました。
これで自分の命を守る準備が整い、安心しています。」
ユーザーIさん(30代男性・サラリーマン)
「通勤時に持ち歩くことができるコンパクトなサイズ感が気に入っています。
会社から自宅までの距離が遠いため、災害時には歩いて帰ることも想定してこの防災グッズを選びました。
防寒具や靴擦れ対策グッズも入っており、想定外の事態にも対応できるのがありがたいです。」
まとめ
これらのユーザーの声からわかるように、防災グッズ39点セットは幅広い状況に対応できるだけでなく、
ユーザーそれぞれの生活スタイルやニーズにも合った工夫が施されています。信頼性の高い製品であり、
実際の緊急時にも役立つアイテムが揃っていることが、利用者から高く評価されています。
購入方法と特典
公式サイトで購入可能です。現在、キャンペーン中でお得な特典やまとめ買い割引が提供されています。
興味のある方は今すぐチェックしてみてください。
防災士厳選の防災グッズ39点セット【ディフェンドフューチャー】
購入するタイミングの提案
防災グッズは、特定のタイミングで購入すると特に効果的です。
例えば、新築祝いとしての贈り物や、家族の安全を守るための地震対策にぴったりです。
また、以下のタイミングを狙って購入するのも賢い選択です:
- 防災の日(9月1日)
- 阪神淡路大震災の日(1月17日)
- 東日本大震災の日(3月11日)
防災グッズに加え、性別や年齢に応じた特定のニーズに応じたアイテムも重要です。
個人ごとに必要な物品を準備しておくことで、緊急時により適切な対応ができ、安心感が増します。
以下に、性別や年齢に応じた追加アイテムとその必要性について解説し、表にまとめました。
防災グッズ以外に性別・年齢ごとに準備しておくべきアイテム
1. 男性向けアイテム
- 常備薬:持病がある場合、普段から服用している薬を多めに準備しておく必要があります。
例えば、高血圧、糖尿病、喘息などの慢性疾患を持っている場合、
それぞれの薬が不足しないように備えておきます。 - 剃刀やシェービング用品:個人的な衛生を保つために必要な物品。災害時にも清潔を保つことは重要です。
2. 女性向けアイテム
- 生理用品:女性にとって必要不可欠な物品です。数日間の避難生活に対応できるよう、
分な量を準備します。災害時には物資が不足することがあるため、長期間を見越して多めに準備すると安心です。 - 女性用衛生用品:ウェットティッシュや消毒液など、個人衛生を保つためのアイテムを備えておくと、
環境が整っていない避難所でも清潔を保つことができます。
3. 乳幼児向けアイテム
- おむつ:乳幼児がいる家庭では、大量のおむつが必要です。
数日分を目安に多めに準備しておくことが推奨されます。 - 粉ミルク・哺乳瓶:授乳期の子どもがいる場合は、粉ミルクや哺乳瓶も忘れずに。
お湯が使えない場合に備えて、常温で使える哺乳瓶も検討しましょう。
4. 高齢者向けアイテム
- 介護用品:高齢者向けには、介護が必要な場合に備えて、紙おむつやリハビリ用品、
必要な薬などを用意します。また、簡単に着脱できる衣類や、
動が困難な場合に使用する杖や歩行器も考慮すべきです。 - 補聴器用の電池や眼鏡の予備:視覚や聴覚に支障がある場合、これらのアイテムの予備を用意しておくことで、
避難生活中も快適に過ごせます。
性別・年齢別に必要なアイテム一覧表
| 性別・年齢 | 必要なアイテム | 詳細 |
|---|---|---|
| 男性 | 常備薬 | 持病がある場合、服用薬を多めに準備 |
| 男性 | 剃刀・シェービング用品 | 衛生を保つために必要 |
| 女性 | 生理用品 | 十分な量を準備。長期間を見越して多めに |
| 女性 | 女性用衛生用品 | ウェットティッシュや消毒液など個人衛生用品 |
| 乳幼児 | おむつ | 数日分の大量の備えが必要 |
| 乳幼児 | 粉ミルク・哺乳瓶 | 授乳期の子ども用に常温で使えるものも考慮 |
| 高齢者 | 介護用品 | 紙おむつ、リハビリ用品、介護が必要な場合の準備 |
| 高齢者 | 補聴器の電池、予備眼鏡 | 補聴器や眼鏡の予備を用意 |
アイテム準備のポイント
- 個々のニーズを考慮する:防災グッズは家族全員に共通するものが多いですが、
年齢や性別によって特定のニーズが異なります。特に女性や乳幼児、高齢者は、
個別に準備すべきアイテムが多いため、災害時に焦らないよう事前に整理しておくことが大切です。 - 量を余裕を持って用意する:物資の供給が滞る可能性が高いため、数日分の予備を持っておくことが安心です。
特に、乳幼児や高齢者向けの物品は十分な量を備えておく必要があります。 - 携帯性を考慮する:避難時にすぐ持ち出せるバッグにまとめることも忘れずに。
必要な物品がすぐに取り出せるよう、普段から整理しておきましょう。
災害時には、各個人のニーズに合わせた物品をしっかり準備しておくことで、避難生活をより快適かつ安全に過ごすことができます。
防災グッズの消費期限が切れた場合の対処法
防災グッズの消費期限が切れた場合、無駄にせず有効に活用するための対処法を詳しく解説します。
防災グッズの多くには、非常食や飲料水、医薬品など消費期限のあるアイテムが含まれており、定期的な点検と交換が必要です。
1. 定期的な点検と交換の習慣化
防災グッズの消費期限を確認することは、定期的な点検と交換を行う上で非常に重要です。
以下の方法で、消費期限切れを防ぎつつ、常に最新の状態を保つことができます。
- 定期的な点検スケジュールを作る:防災グッズの点検は年に数回行うのが理想です。
たとえば、防災の日(9月1日)や、季節の変わり目などに合わせて点検を行うと、習慣化しやすくなります。 - 交換前提の購入:防災グッズを購入する際に、消費期限が比較的長いものを選ぶと同時に、
交換のタイミングを把握しておきましょう。非常食や水は5年~10年の保存が可能なものが多いですが、
消費期限が近づいたら余裕をもって交換します。 - 交換日をメモしておく:防災グッズには交換日を記録し、カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を使って、
交換日を知らせるようにします。これにより、忘れずに定期的な交換が可能です。
2. 消費期限が切れた防災グッズの有効活用法
消費期限が切れそうな防災グッズや切れてしまったものも、
無駄にせず活用することができます。以下の方法を参考にしてください。
a. 日常生活での使用
消費期限が迫っている防災グッズは、日常生活で使用することで無駄を防げます。
- 非常食の消費:保存期間が長い非常食や飲料水も、通常の食事やアウトドア活動などで消費することが可能です。
賞味期限が切れる前に、キャンプやピクニック、家庭での非常食試食日を設け、
実際にどのような味かを確認しながら使い切りましょう。 - 救急用品の消費:医薬品や衛生用品も、日常で使える場面が多くあります。
古い包帯や消毒薬は、家庭内の小さなケガに使うことで、期限切れ前に有効活用できます。
b. 地域の福祉施設や支援団体に寄付
消費期限が切れそうな防災グッズを有効活用する方法の一つとして、地域の福祉施設や支援団体への寄付があります。
防災グッズや非常食を必要としている施設や団体は多いため、寄付することで防災意識の向上にも貢献できます。
- 寄付を受け付けている施設を調べる:事前に、どの施設や団体が消費期限が近い非常食や衛生用品を受け入れているかを調べ、確認します。
- 適切な寄付タイミング:消費期限が過ぎる前に寄付することが重要です。
賞味期限が半年~1年残っている状態で寄付することで、受け取った施設でも十分に活用してもらえます。
c. 防災訓練での使用
地域や家庭で実施する防災訓練の際に、消費期限が近い防災グッズを使用するのも一つの方法です。以下のような場面で役立ちます。
- 防災訓練のシミュレーション:防災訓練中に非常食を試食したり、
救急用品を使って応急処置の練習をしたりすることで、実際の使用感を確かめることができます。
また、避難時に持ち出す荷物の重さや、使用する際の手順も確認できるため、災害時に備えた有益な経験となります。 - 訓練での共有:学校や職場、地域コミュニティで実施する防災訓練に古くなった防災グッズを提供し、
参加者全員でその使用方法を学びます。
3. 消費期限が切れた防災グッズの交換方法
防災グッズは、消費期限が切れたら必ず新しいものに交換しましょう。以下は、効率的に交換する方法です。
- 一部の防災グッズには交換サービスがある:企業によっては、期限切れの防災グッズに対して、
交換サービスを提供している場合があります。購入時にそのようなサービスがあるかどうかを確認し、利用すると安心です。 - セットでの交換がおすすめ:期限切れの個別アイテムごとに交換するよりも、まとめてセットで交換する方が効率的です。
特に防災セットには複数のアイテムが含まれているため、期限が近いものを一括でチェックして交換します。
まとめ
防災グッズの消費期限が切れてしまった場合でも、日常での使用や寄付、防災訓練での活用など、
多くの方法で無駄にせず有効に活用できます。また、定期的な点検と交換を心がけることで、
非常時に備えた最良の状態を保つことができ、安心感が増します。
災害時の基本的な避難行動:知っておくべき4つのステップ
災害時に冷静で迅速な行動を取ることは、命を守るために非常に重要です。
以下の4つのステップを押さえておけば、いざという時に適切な判断ができます。
1. 揺れが収まってから避難する
地震が発生した際、まず大切なのは「慌てて外に出ない」ことです。大きな揺れが続いている間は、
建物の中に留まり、以下のような対策を取るべきです。
- 頭を守る:本棚やガラスが倒れたり割れたりする可能性があるため、クッションや防災ヘルメット、
最悪でも腕で頭を覆いましょう。 - 安全な場所に移動:机の下に隠れたり、丈夫な家具のそばに身を寄せることで、揺れによる落下物から身を守ります。
- 火の始末:可能であれば火元を消すことが望ましいですが、身の安全を最優先に行動しましょう。
揺れが収まったら、冷静に避難を開始します。家の中や周囲の状況を確認し、二次災害に巻き込まれないように注意します。
2. 海や川の近くにいる場合は高台へ避難
津波のリスクが高い地域にいる場合、地震発生後すぐに高台や、少なくとも3階以上の建物に避難しましょう。
- 沿岸部では直後の津波を警戒:津波は地震の直後に発生する可能性が高く、地震後に海岸近くにいると非常に危険です。
- 避難の際には徒歩で:車での移動は渋滞を引き起こすだけでなく、避難路の確保も妨げてしまう可能性があるため、徒歩での避難が基本です。
3. 隣近所に声をかけ、助け合って避難する
災害時はパニックが起こりやすいですが、助け合いが重要です。
避難する際は、周囲の人にも声をかけ、共に安全な場所へ避難することを心がけましょう。
- 独居の高齢者や障害を持つ人々を助ける:自分が無事である場合、特に高齢者や体が不自由な方の避難をサポートします。
- 情報を共有する:ラジオやスマホで得た情報を周囲に伝え、適切な避難経路や場所を共有しましょう。
4. 頭を守りながら避難し、避難経路に注意を払う
避難中に落下物がある場合は、帽子や手で頭を覆うようにし、安全を確保しながら進みます。
また、避難路に危険が潜んでいる可能性があるため、足元にも注意を払いながら避難します。
- 電柱やブロック塀に注意:揺れで倒壊する可能性のあるものには近づかないようにし、安全なルートを選びましょう。
- 避難場所の確認:日頃から避難場所を確認し、避難経路を家族全員で共有しておくことが大切です。
災害発生後の72時間:生き抜くための詳細ガイド
災害発生直後の72時間(3日間)は、救助が届くまでの最も重要な時間です。
この期間をどう過ごすかによって、命を守るための鍵が握られます。
以下に、1日目から3日目までの過ごし方を詳しく解説します。
1日目:安全確保と情報収集が最優先
1. 自分の安全を確保する
- まずは落ち着いて行動:地震や災害直後は慌てがちですが、冷静に行動することが大切です。
家の中の危険箇所(倒壊の恐れがある家具やガラスなど)から遠ざかり、安全な場所に移動します。 - 避難ルートの確認:家族や近隣の状況を確認し、避難が必要な場合は速やかに避難所に向かいます。
2. 必要な物資を確保する
- 非常食と飲料水を確保:1人1日につき3リットルの水を確保するのが理想です。
非常食もできるだけカロリーの高いものを選び、体力を保つよう心がけます。 - 緊急キットの活用:防災グッズ39点セットに含まれている飲料水や食料、防寒具を使用し、体調を整えます。
3. 正確な情報収集
- ラジオやスマホで情報を得る:通信が遮断されている場合は、防災ラジオが非常に役立ちます。
政府や自治体からの最新情報を確認し、避難場所や物資の供給状況を把握します。 - 停電時の備え:懐中電灯や予備バッテリーを用いて、暗い中でも安全に行動できるようにします。
2日目:体力と体温の維持に努める
1. 体温を維持する
- 防寒具の使用:特に夜間は気温が急激に下がることがあるため、毛布や防寒シートを使って体温を保持します。
防寒シートは軽量で持ち運びやすく、非常に効果的です。 - 濡れた場合は早急に乾かす:水濡れは低体温症のリスクを高めます。
乾いた衣服に着替え、体温の低下を防ぎます。
2. 休息をしっかり取る
- 過労を避ける:緊急時だからといって無理をすると体力が持ちません。
短時間でも休息を取り、疲労を溜めないようにします。 - 非常食でエネルギーを補充:非常食を定期的に摂取し、エネルギーを補給します。
湯を使わずに食べられるものや、簡単に開封できる食品を優先して消費します。
3. 周囲との協力
- 避難所での協力:避難所に到着した場合、周囲の人々と協力して行動します。
情報を共有し、共助の精神で物資を分け合うことが大切です。 - 助け合いの精神:避難所では、他の避難者とともに物資や情報を分け合い、必要があれば自分からも支援を申し出ます。
3日目:救助を待つための準備
1. 救助されやすい場所に移動
- 目立つ場所にいる:できるだけ目立つ場所で待機し、救助隊に発見されやすいようにします。
屋外にいる場合、ヘリコプターが確認しやすい開けた場所や建物の上層階に移動することが効果的です。
2. サインを送る
- ホイッスルやライトで存在をアピール:防災キットに含まれているホイッスルや懐中電灯を使い、
救助隊に自分の存在を知らせます。夜間でも目立つように、定期的にライトを点滅させることが有効です。
3. 冷静な判断を保つ
- 焦らず待機:無理に動き回らず、体力を温存しつつ、救助を待ちます。
移動するときは状況をよく確認し、他の人に危険が及ばないよう慎重に行動しましょう。 - 冷静に状況を分析:救助が遅れている場合でも、パニックに陥らず、体力を温存しながら冷静に状況を判断します。
移動が必要な場合や、助けを呼ぶ手段を再度検討し、安全を確保しながら行動しましょう。
災害時に生き抜くための追加ポイント
1. 自然災害に応じた避難行動の違い
災害には地震、台風、豪雨、火災、津波などさまざまな種類があります。
それぞれに応じた避難行動を事前に学んでおくことで、適切な対応が取れるようになります。
- 地震:上記で説明したように、まずは揺れが収まるまで安全を確保し、落下物に注意して避難します。
- 台風・豪雨:低地や川沿いでは洪水や土砂災害のリスクがあるため、事前に安全な高台に避難します。
- 避難勧告が出た場合は、速やかに従いましょう。
- 火災:火災時は煙を避けるため、ハンカチなどで口と鼻を覆い、低い姿勢で避難します。
- 火元から距離を取ることが最優先です。
- 津波:地震後に津波のリスクがある地域では、高台や3階以上の建物に迅速に避難することが不可欠です。
2. 災害に備えるための日常の準備
日頃からの備えが災害時の行動をスムーズにし、命を守ることにつながります。
- 避難場所の確認:自宅や職場の近くにある避難場所を事前に確認し、家族全員で共有しておくことが大切です。
- 非常持ち出し袋の準備:最低限の食料・水・医薬品・衣類などが入った非常持ち出し袋を、
いつでも取り出せる場所に準備しておきましょう。防災士監修の39点セットも、こうした準備に役立ちます。 - 避難経路の確認:建物や地域ごとの避難経路を事前に把握し、避難の際にどのルートを通るべきか決めておきます。
- 家族との連絡方法:災害時には通信インフラがダウンする可能性も高いため、連絡手段や集合場所をあらかじめ決めておくと安心です。
防災意識を高め、適切な準備を整えておくことで、災害時に冷静で安全な行動が取れるようになります。
防災士が厳選した防災グッズ39点セットも、こうした備えの一部として大いに役立つアイテムです。
ぜひ日常から防災対策を心がけ、家族や大切な人を守るための準備を進めましょう。
結論
防災士が厳選した「防災グッズ39点セット」は、家族の安全を守るための最良の選択です。
いつ何が起こるかわからないからこそ、今すぐ備えておくことで安心を手に入れましょう。